OpenAI 新モデル「o3-mini」をリリース!あなたは既存モデルとの使い分け方を知っている?
- 石黒翔也
- 2月4日
- 読了時間: 4分

OpenAI、新推論モデル「o3-mini」をリリース!
STEM分野(Science, Technology, Engineering, Mathematicsの略で、科学・技術・工学・数学の分野を指す)に最適化された最新AIモデル
2025年2月4日、OpenAIは新たな推論専用モデル「o3-mini」を発表しました。このモデルは、特に科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、数学(Mathematics)のSTEM分野(Science, Technology, Engineering, Mathematicsの略で、科学・技術・工学・数学の分野を指す)における推論能力を強化し、従来のモデルと比べて高速かつコスト効率に優れたAIとして設計されています。
o3-miniの主な特徴
高い推論能力
「o3-mini」は、特に数学的推論やコード生成において優れた性能を発揮し、複雑な問題を段階的に解決する能力を備えています。OpenAIの発表によると、科学的問題の解決やプログラミング支援において特に有効だとされています。
従来モデルより約24%高速な応答
処理速度の向上により、リアルタイムでの推論がよりスムーズに行えるようになりました。これにより、ユーザーはストレスなくAIの推論を活用できます。
コストパフォーマンスの向上
o3-miniは、高い推論性能を維持しながらも、従来モデルに比べてコストを抑えることに成功しています。特に、企業や開発者向けに低コストでのAI活用を促進することが期待されています。
柔軟な推論設定(Reasonレベルの選択)
OpenAIは、o3-miniに低・中・高の3つの推論レベルを導入し、タスクの複雑さや必要な精度に応じて調整可能にしました。これにより、ユーザーは用途に応じた最適な推論を利用できます。
o3-miniの利用方法
ChatGPTの無料ユーザーは、メッセージ作成時に「Reason」を選択することでo3-miniを試すことができます。また、有料プラン(Plus、Team、Pro)のユーザーは、o3-miniやo3-mini-highを選択して、より高度な推論能力を体験可能です。
o3-miniと既存モデル(GPT4o・o1)との使い分け
OpenAIには複数のAIモデル(GPT-4o、o1、o3-mini)が存在します。
しかし、このモデルの違いについて説明できる人は少ないのではないでしょうか?
大きな違いはGPT-4oがプリトレーニングされているモデルであるのにも関わらず、o1とo3-miniは推論できるモデルだということです。
この違いにより、それぞれのモデルの活用方法が大きく異なります。
ChatGPT-4o:プリトレーニングされたモデルで、インターネット上の情報を学習し、広範な知識を持っています。精度が高く、長文生成や複雑な分析に優れています。科学研究、クリエイティブな執筆、精密なデータ分析など、既存の知識に基づく高度なタスクに適しています。
o1:推論能力を持つモデルで、科学的問題解決やプログラミング、数学的推論に特化しています。新しい研究や未知の分野において、新たな発見を促進する可能性があります。
o3-mini:推論専用モデルとして設計されており、高速かつコスト効率に優れます。簡単な推論タスクや軽量なコード生成、数学計算に適しており、短時間での解決が求められる場面で効果的に活用できます。
このため、GPT-4o は既存の知識をベースにした作業に、o1・o3-mini は未知の領域に挑戦する場面で活用するのが最適なアプローチとなります。
プリトレーニングとは何か?推論とは何か?を詳しく知りたい人は、以下の記事で詳しく解説しています。
AIの最先端を行くソフトバンクグループの孫正義氏が、ソフトバンクワールド2024で詳しく語っています!これ以上分かりやすく解説しているところはありませんので必読です。
【合わせて読みたい記事】
孫正義の超知性ビジョンとは?ソフトバンクワールド2024で語られたAIと人類の未来
o3-miniの活用と業務効率化の可能性
今回発表された o3-mini は、特に 高速な推論能力 を活かした業務自動化に大きな可能性を秘めています。たとえば、社内のルーチン業務や問い合わせ対応をAIで自動化できれば、より本質的な業務に集中できるようになります。
実際、企業では AIによる問い合わせ対応の自動化 が進んでおり、例えば 「AIbox」 のようなツールを活用すれば、社内のFAQやマニュアルをもとにAIが自動で回答を生成し、サポート業務の負担を軽減できます。
社内の問い合わせ対応をAIで効率化したい方はこちら → AIbox公式サイト
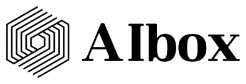
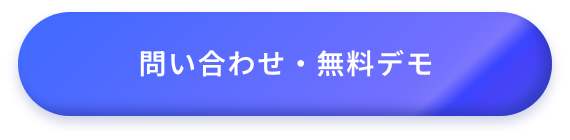




.jpg)
Comments