Napkin AIとは?無料で使える図解生成AIツールの全貌【使い方も解説】
- 石黒翔也
- 2 日前
- 読了時間: 5分

Napkin AI(ナプキンエーアイ)とは、誰でも簡単に図解(ビジュアル)を自動生成できる無料のAIツールです。特に注目されているのが「Canvas(キャンバス)」機能で、テキストを入力するだけで、AIがマインドマップやフローチャートなどの構造的な図を自動作成してくれます。ノーコードで使えるのが大きな特長で、「Napkin AI 無料」や「Napkin AI 使い方」といったキーワードで多くの方が検索しています。
本記事では、Napkin AIの使い方や活用シーン、得意・不得意、Canvas機能の詳細まで、初心者にもわかりやすく解説します。
Napkin AIの得意なこと・不得意なこと
得意なこと
スピーディな図解生成:文章ベースのアイデアや概念を数秒で構造的な図に変換できます。
直感的UIとノーコード操作:専門的な知識がなくても誰でも扱える操作性。
自動レイアウト調整:ノードやリンクが複雑になってもAIがバランスよく再配置。
軽量なアウトプットの共有:リンク共有や画像エクスポートで社内外への伝達が容易。
日本語対応のAI入力:英語に限らず、日本語でも自然文を図解に変換できます。
不得意なこと
高度なビジュアル表現の制限:図の装飾性やブランドカラーの細かい統制には限界があります。
ノードが増えた際の視認性低下:100個を超えるノードを扱うと情報の把握が難しくなることも。
階層構造や複雑なUI設計への弱さ:あくまで説明・概念可視化に向いており、UIプロトタイピングには不向き。
インポート機能の非対応:外部ファイル(CSVやXMindなど)からのデータインポートには現時点で非対応。
🧪 Napkin AIで複雑な図解にチャレンジしてみた
Napkin AIの魅力は、シンプルな文章から自動で図解を生成してくれる点にあります。
今回は「どこまで複雑な構造に対応できるのか」を検証するために、以下のような多階層の業務プロセス図をテキストで入力してみました。
新規顧客獲得 → ヒアリング → 要件定義(部門A、B、Cの調整) → 提案書作成 → 社内レビュー(法務・営業・経理) → 提案書修正 → クライアント説明 → 受注 → キックオフミーティング(PM、デザイナー、エンジニア) → 各フェーズ管理(設計・実装・検証) → 納品 → 保守対応
生成された画像がこちらです。

Napkin AIは入力された文章をもとに、ある程度自動的にノードとリンクを作成してくれました。しかし、「受注」の工程以降が生成されない状態となってしまいました。
また、何度か試しているうちに以下のような課題が出てきました。
分岐(A or B)や階層構造(部門ごとの処理)が表現しきれない
8ステップ以上の工程でレイアウトが崩れやすい、または省略されてしまう
AIが一文ずつ処理するため、文の構造が複雑すぎると正確に反映されない
ノードが増えると、視認性が大きく下がる(とくにスマホ画面では厳しい)
Napkin AIが特に使えるシーン
Napkin AIは、Web記事やプレゼン資料の図解にとても相性が良いと感じました。難解な内容でも、図として可視化することで読者や相手に伝わりやすくなり、特にブログや動画の補足、社内の共有資料、教育コンテンツの整理に重宝します。
また、AIで出力した内容をそのまま図にできる点も便利で、思考の整理や議論の見える化に最適なツールだと思います。
Web記事・動画での図解補足:ブログやYouTubeでの難解な説明を図として提示することで、読者や視聴者の理解を促進。
社内会議・ワークショップ:意見をリアルタイムで図に起こし、議論の見える化を実現。
プレゼン・営業資料の下書き:プロトタイプ段階の図を作ることで、内容構造のレビューが容易に。
教育コンテンツの設計:学習プロセス、論理構造、因果関係を明示化して、教材として活用。
思考の可視化と整理:ブレインストーミングや戦略立案時に、漠然としたアイデアを整理整頓。
AI出力の視覚化:ChatGPTやClaudeなどのLLMによる出力結果をNapkinに入力して、要素の関係性を図で確認。
1. 表現可能な図解の種類(形式)
Napkin AIが自動生成・手動作成可能な形式は多岐にわたります:
マインドマップ形式:中心概念から放射状にアイデア展開。
フローチャート形式:工程や処理手順を視覚化。
因果関係図:「AがBを引き起こす」といった構造を表現。
SWOT・マトリクス図:2軸分類を用いた戦略分析に活用。
タイムライン図:時系列に沿って要素を並べてストーリー化。
コンセプトチャート:抽象的な概念群を整理し相互関係を図示。
AIが文脈を解析し、最も適した形式を提示してくれるため、形式選定の手間も軽減されます。
2. エクスポート・共有機能
完成した図解はさまざまな形式で出力可能です。
画像形式:PNG / SVG / PDF で出力して資料貼り付けや印刷に対応。
リンク共有:クラウド上のキャンバスをURLで他者と共有、閲覧・編集も可能(権限設定あり)。
チームコラボレーション:Proプランでは共同編集やコメント機能が有効化。
変更履歴のトラッキング:Undo/Redoや時系列での変更履歴が保存され、戻すことも可能。
Markdown出力(実験的):図解の構造をテキスト化し、ドキュメントに転用可能。

Napkin AIの基本的な使い方(無料でOK)
Napkin AIは現在、無料プランでも十分に活用できます。以下の手順で簡単に始められます:
公式サイトにアクセス(https://www.napkin.ai)
「Get Napkin Free」から無料アカウントを作成(GoogleアカウントでもOK)
ダッシュボードから「New Canvas」を選択
テキストでアイデアや構造を入力(例:「マーケ戦略 → 顧客行動」)
AIが自動で図解化 → 必要に応じてノードやレイアウトを調整
生成された図は、PNGやPDFで保存できるほか、共有リンクで他者と共有することも可能です。
業務効率化を“図解”から“問い合わせ対応”まで広げるなら「AIbox」もおすすめ
Napkin AIが「思考の可視化」や「図解による伝達」に優れているように、日々の業務効率を上げるためには“情報の整理”と“共有”がカギになります。
もし、社内や顧客からの問い合わせ対応に時間を取られているなら、次に取り入れたいのが**問い合わせの自動対応AI「AIbox」**です。
AIboxは、マニュアルやFAQ、過去の問い合わせ履歴を一括管理し、AIが質問に即時対応してくれるツール。Slackと連携すれば、Slack内の情報まで検索・回答可能になるため、社内の「これ誰に聞けばいいんだっけ?」が一気に解消します。
詳しくはこちら ▶︎ https://www.ai-box.biz/
是非お問い合わせください!
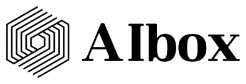
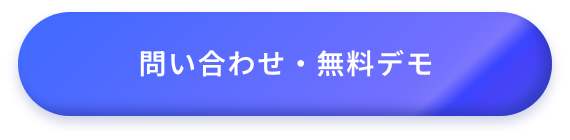

.jpg)
Comments