AI・自動化ツール導入で業務効率はどれだけ変わる?使う企業・使わない企業の“リアルな差”とは
- 4月9日
- 読了時間: 7分

AI・自動化ツールを使うか、使わないか——その選択が生産性を大きく分ける
「最近よく聞くAIって本当に役に立つの?」「自社のような中小企業でも使えるのだろうか?」そんな疑問を持つ方も多いはずです。
結論から言えば、AIや自動化ツールを業務に取り入れることで、業務効率は劇的に向上します。
しかも、これは一部の大企業やIT企業に限った話ではありません。中小企業でも、個人でも、AI・自動化ツールの導入によって「時間の節約」や「生産性の向上」が現実のものとなっています。
本記事では、AIや自動化ツールを「使った場合」と「使わない場合」で業務効率がどう違うのかを、具体的な事例を交えて紹介していきます。読了後には、あなたの業務にもAI・自動化ツールを活かせるヒントが見つかるはずです。
AI・自動化ツール未導入企業の現実:ルーティン作業に追われる日常
まずは、AI・自動化ツールを使わないことで生じる「日常のムダ」を見てみましょう。どれも、ちょっとしたことのようで、年間にすると膨大な時間ロスにつながっています。
1. 手作業の多さによる時間ロス
請求書作成・送付業務
請求書の作成に時間がかかると回答した企業は30.0%、印刷・捺印・郵送の手間を課題と感じている企業は25.8%に上ります。
紙の請求書を作成・封入・郵送している企業では、1通あたり1.5〜2分かかるといわれています。仮に月500通を処理する場合、これだけで毎月12.5時間以上の手間に。
加えて、請求漏れや金額ミス、郵送トラブルなどのリスクも発生します。
参考:楽楽明細コラム
顧客からの問い合わせ対応
Zendesk社の調査によれば、カスタマーサポートにおける1件あたりの平均初回対応時間は約6分。問い合わせ対応を経験したことがある方なら、初回対応から調査・確認・回答作成を含めると1件あたり10分くらいはかかる、またはそれ以上かかると感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
参考:zendeskブログ
会議の議事録の手動によるまとめ時間
PRTIMES社の調査によると、議事録の作成にかける1週間あたりの平均時間は6.13時間、年間に換算すると319.6時間にも達します。
また、議事録作成に負担を感じている方は67%にもなり、業務効率が悪くなる原因にもなり兼ねません。
参考:PRTIMES調査
こうした業務は、実はAIや自動化ツールで簡単に自動化できるものばかりです。にも関わらず、多くの企業では**「今まで通りのやり方」にこだわるがゆえに**、毎日何時間も非効率な作業に時間を割いてしまっています。
解決に使えるAI・自動化ツール
請求書作成・送付業務
マネーフォワード クラウド請求書:作成〜郵送代行までクラウドで完結。経理業務全体と連携可能。
freee請求書:直感的UIで簡単に請求書作成。取引先管理とも連携でき、業務がスムーズに。
顧客からの問い合わせ対応
Zendesk + AIチャットボット連携:ナレッジベースと連動し、FAQや一次対応を自動化。
Helpfeel:検索性に優れたFAQ自動応答ツール。人力対応を最大80%削減可能
ChatGPT API + Notion:社内ナレッジベースを活かした自作チャットボットにも活用可能。
会議の議事録作成
Notta:日本語対応の音声文字起こしツール。ZoomやTeams連携も可能で、議事録を即自動生成。
Otter.ai:リアルタイムで音声を文字化し、要約も自動生成。英語会議に最適。
AIGIJIROKU:議事録作成に特化した日本製AIサービス。発言者識別や要点抽出機能が優秀。
2. 属人化とミスのリスク
人がやる作業にはミスがつきものです。特に、単純作業を長時間続けることで集中力が落ち、ミスや漏れ、確認漏れが発生しやすくなります。
また、その人しかできない作業が多いと、休んだり辞めたりした時のリスクが大きく、組織全体の安定性にも影響します。
AI・自動化ツールの導入による業務効率の例
それでは、AI・自動化ツールを導入することで実際にどのような変化があったのか、例をいくつか紹介します。
・ チャットボットで顧客対応を自動化
チャットボットを導入している多くの企業では、毎日寄せられる問い合わせに人力で対応していました。しかし、AIチャットボットを導入したことで、24時間365日対応が可能になったり、対応時間の大幅な短縮、スタッフの数を増やすことなく以前は取りこぼしていたコンタクトのフォローアップができるようになったなど、多くの成果が出ています。また、担当者はクレーム対応など、より重要な業務に集中できるようになります。
・ RPAによる定型業務の自動化
RPAの導入は、地方自治体でも取り組んでおり、少子高齢化による人口減少が進む昨今、定型的な業務の自動化の効率化や正確性を保つ有効的な手段となっています。
勤怠集計や給与計算、見積書作成、分析データの収集など定型業務をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で自動化し、月間で70時間以上の作業が削減されたという事例もあります。
多岐にわたる業種・部門での導入効果が期待できます。
RPAで効率化できる業務の洗い出しをすることで「この作業は本当に必要なのか」「同様の作業を繰り返している」などの課題もわかる良い機会になるでしょう。
・生成AIで報告書作成
生成AIでは、文書作成のほか、翻訳、文章の要約などができます。これらの機能を活用し、文書作成業務の大幅な効率化が可能です。
例えば、営業部門で導入した場合、提案書や会議報告書のドラフト作成をAIが担当することで、作業時間を短縮しながら、質の高い文書を素早く作成できます。提出資料の下書きやメール文の作成などを短時間で行えるようになります。また、長文の要約や翻訳も迅速にできるなど、業務を大幅に効率化します。
最終チェックだけ人が行うことで、効率とクオリティの両立を実現することができます。
導入を成功させるためのポイント
AI・自動化ツールを導入しても「思ったほど効率が上がらなかった」「導入したツールと業務があっていなかった」となるのは、正しいステップを踏んでいないからです。以下の3つのコツを押さえておきましょう。
1.導入目的の明確化
導入によって目指すものが何であるのか、目的を明確にすることが必要です。それにより検討範囲や優先度が変わってきます。
従業員の負担軽減、コスト削減、人為的ミスの削減、サービス向上など、目的により体制や検討範囲が変わってきます。
2. 業務の洗い出し
現在の業務の洗い出しをすることで、導入目的に沿う業務の整理が可能になります。「請求書作成」「議事録」「提案書」「見積書」など、ルーチンワークで工数が明確な業務から試してみることで成果が見えやすいでしょう。
3. 社内に理解を広げる
導入後、社内での利用促進がうまくいかないことはよくあることです。一部の方しか使わない、使えないのでは期待している効果は得られません。トライアル期間のあるサービスを活用し、事前の周知や自社の業務特性・ITリテラシー・コスト感に合っているのか意見交換をすることで失敗のリスクを最小限に抑え、導入後の活用がスムーズになります。
AIは“業務の味方”、まずは一歩を踏み出そう
AIを導入することで得られる最大のメリットは、「時間」という資源を手に入れられることです。
その時間を使って、次のような”本来やるべき仕事”に集中できるようになります。
– お客様の“声”に耳を傾け、サービスの質の改善
– 提案書やプレゼン資料のブラッシュアップ
– PDCAを回し、業務改善や成果創出に直結する行動
– 社員のキャリアアップやスキルアップ
– 競合調査・市場調査など、未来の収益づくりに集中
今までの習慣を変えることは、初めは時間がかかってしまうものです。しかし、それを新しい習慣に変えることで業務効率化を実現していけると考えます。社内や部門全体で取り組むことにより効果的でスピーディな改善をすることが期待できるのではないでしょうか。
AI導入の第一歩に、最適なツールを選ぶという選択
AIを活用すれば業務効率は劇的に向上し、「本来やるべき仕事」に集中できる環境が整います。とはいえ、最初の導入でつまずく企業も少なくありません。
そんな中、**「まずは小さく始めたい」「成果が見えるところから取り組みたい」**と考える企業に選ばれているのが、**社内問い合わせ対応を自動化できるAIツール「AIbox」**です。
AIboxは、FAQ・マニュアル・過去の問い合わせ履歴など、社内に散らばる情報をAIに読み込ませ、まるで経験豊富な担当者のように正確な回答を即時返すことができます。
Slackとの連携にも対応しており、社員が普段使っているチャット上で自然に問い合わせが完結。さらに、AIの回答には必ず根拠となる参照元データも表示されるため、信頼性も抜群です。
「問い合わせ対応に毎日追われている」「人によって回答がバラバラ」「教育しても辞めてしまう」——そんな悩みを抱えるカスタマーサポート部門やバックオフィス部門の負担を、大幅に軽減します。
💡 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://www.ai-box.biz/
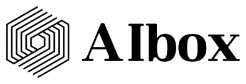
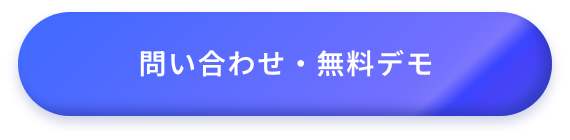

.jpg)
Comments